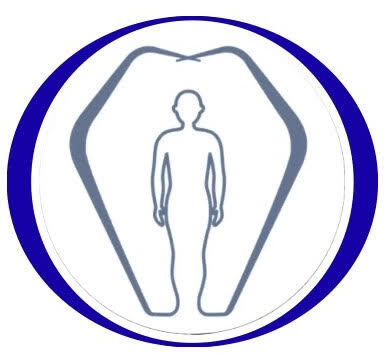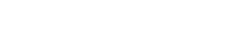近日中に、Dr.Ryoのブログが朝日新聞に掲載されます。
2025年11月19日
朝日新聞に掲載された内容は、文字数の制限の関係上、要約版としての掲載ですが、今回はその拡大版を、国内外の有名な大学の論文を参考にしながらご紹介します。
原因不明の倦怠感に悩む大学生へ

「二十歳の大学生です。最近、倦怠感が強くて、朝なかなか起きられません。学校に行くのもつらくて、ネットで調べて、いくつかの複数の病院を受診しましたが、原因不明と言われました。これから、私はどうすればいいでしょうか。アドバイスをお願いします」
実は、当院では、最近、このような相談を受けることが増えています。
結論からいいますと、大丈夫です。まだ回復の可能性は十分にあると思います。
これは、気休めではありませんから、焦らず、私の話を最後まで聞いてください。
そうすると、今までにない、新しい治療のアプローチが見えてくると思います。
原因が分からない、と言われたら、、、

体調不良で、複数の診療科を受診しても異常が見つからない場合、多くの方が、もしかしたら気のせいかもしれないとか、自分の身体が弱いだけなのかもしれないとか、それとも精神的な問題かも、と考えると思います。
しかし、明らかに身体の不調があるのであれば、それは気のせいではなく、私の経験上、必ずどこかに問題があることが多いのです。
そして、その問題が、どこから来ているのかを正しく分析して、その原因を見極める新しい診断スキルが必要になってきます。
私の臨床経験では、「歯科的な要因」が隠れているケースが少なくありません。
例えば、咬み合わせのわずかなズレや、合っていない被せ物、夜間の歯ぎしり、食いしばりなどが、顎から首、肩、頭部へと筋肉と神経を通じて負担を広げて、姿勢や平衡感覚を乱すことがあるのです。
そのことを放置すると、強い倦怠感、立ちくらみ、頭痛、集中力の低下というような全身の不調が現れることがあります。
歯と身体は、一見、そこまで関係するように見えませんが、実際は密接につながって関係していふのです。
そして、病院の検査で異常なしと言われた時、見落とされがちな、このつながりに目を向けてみる必要があると考えています。
咬み合わせと全身のつながり

スペインのバルセロナ大学の研究チームは、咬み合わせが姿勢と体のバランスにどのように関係するかを調査した結果、咬み合わせの状態が安定している人は、身体の平衡維持がしやすく、姿勢の揺れが少ない傾向があると報告しています。(Julià-Sánchez S. et al., Univ. de Barcelona, 2021)
また、バレンシアのカトリック大学の研究では、かみ合わせのずれがある人は、姿勢の重心線がずれやすく、歩行中の荷重バランスに差が出ることが示されています。(Carda-Navarro I. et al., Sensors, 2024)
ブラジルのサンパウロ大学の研究では、口腔内の健康と全身疾患の関係が取り上げられています。歯周病や噛み合わせの異常が、循環器、代謝、神経機能にまで影響を及ぼす可能性があるということです。(University of São Paulo, Journal of Oral Science, 2023)
これらの研究は、咬み合わせだけで全身が良くなると、断言するものではなく、無視できない要因になると、しているのです。
つまり、かみ合わせが少しズレて、体がそのズレを補正しきれないと、慢性的な疲労や姿勢の乱れとして現れるわけです。
倦怠感を改善する5つのステップ

ここからは、日常で実践できる回復のステップをご紹介します。
① 睡眠のリズムを安定させて一定に。
実は、眠りの長さより眠りのリズムを整えることの方が重要なのです。就寝と起床の時刻を毎日同じにするだけで、自律神経の乱れが整って、倦怠感が軽減するという研究もあります。
スマートフォンの光を寝る1時間前から避けて、朝は日光を浴びるという習慣は、体をリセットさせて、再起動するスイッチになります。
② 食事を「噛むこと」から整える
柔らかい食べ物ばかり食べると、咀嚼筋が衰えて姿勢筋のバランスが崩れます。
よく噛むことは、栄養摂取の問題でなく、脳を活性化させる大切な刺激です。
噛みごたえのある野菜やたんぱく質を積極的に取り入れることがオススメです。
③ 姿勢と体幹を整える
顎は体幹の真上にあり、猫背や巻き肩になることで、顎の位置がずれて、咬み合わせが乱れてきます。
背中と股関節を中心に伸ばすストレッチを毎日5分くらい続けるだけでも、首や顎への負担が軽くなります。
④ 歯科医院で噛み合わせと、顎の状態を確認
歯は痛くないけど体がつらいというときほど、歯科のチェックが役立ちます。
実は、被せ物や詰め物の高さのわずかな違いや段差が、噛むときの筋の活動を変えて、姿勢まで影響することがあるなです。
必要に応じてナイトガードを使用することも必要です。
⑤ 経過を見える化
症状の変化を記録することも、回復の第一歩になります。
朝、昼、夜の疲労度、立ちくらみ、睡眠時間、噛みしめの自覚を日誌に書くだけで、医療に対して、客観的に見れるようになります。
継続ケアの重要性

私が統括している「トータルヘルスケアプログラム®」では、初回の精密分析の後、1〜3年単位で再分析とフォローアップを行っています。
理由はシンプルです。
人の体は一度整えて終わりではなく、日々の生活の中で少しずつ僅かながら変化していくからです。
ある研究でも、継続的で、個別化された支援が、慢性的な症状の安定化に寄与することが示されています。(Wolff J.L. et al., Johns Hopkins University Public Health Review, 2025)
実際に、プログラムを1年で終えた方よりも、2〜3年継続された方の方が、再分析時のデータで姿勢の安定度や筋緊張の改善が持続している傾向が確認されています。
治ったから終わりではなく、良くなった状態を身体に定着させることが、本当の意味での回復だと考えています。
体が教えてくれる小さなサイン

倦怠感は、怠けではなく、身体が守りに入りたいと訴えるサインであるのです。
気のせいだろうと、無理に元気をつくろうのではなく、体の些細な声を正確に拾うことが健康への第一歩になります。
次の一歩として、できることは、多くありません。
具体的にできることとして、寝る時間を30分早める、朝の通学で一駅分歩いてみる、噛みごたえのある食べ物を積極的に摂る、歯科医院でかみ合わせを確認してみるとかでしょうか。
このような小さな行動の積み重ねが、回復の方向を確実に変えていくのです。
私は、そのみなさんの小さな歩みを、医学と歯科の両面から支えていきたいと考えています。
焦らず、自分のペースで、自分の体を信じて、一歩ずつ確実に進んでください。
その先に、あなたの明るい未来があるのです。
コラムは ウエスト歯科クリニック と 玉川中央歯科クリニック で、それぞれ異なる内容を掲載しています。ぜひ、もう一方のコラムもあわせてご覧ください。
参考文献
- Peres M.A. et al. Oral diseases: a global public health challenge. The Lancet (2019).
口腔疾患と全身健康・生活の質の関連を包括的に示す世界的レビュー。 - World Health Organization. Global Oral Health Status Report (2022).
世界各国における口腔健康の現状と予防的介入の重要性を整理。 - Julià-Sánchez S., Álvarez-Herms J., Burtscher M. Dental occlusion and body balance: A question of environmental constraints? Univ. de Barcelona (2021).
- Carda-Navarro I. et al. Relationship between Body Posture and Dental Occlusion. Sensors 24(6), 1921 (2024).
- Michelotti A., Farella M. et al. Dental occlusion and posture: an overview. Prog Orthod (2011).
- Wolff J.L. et al. Long-Term Care Services and Supports Needed for Successful Aging-in-Place. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (2025).