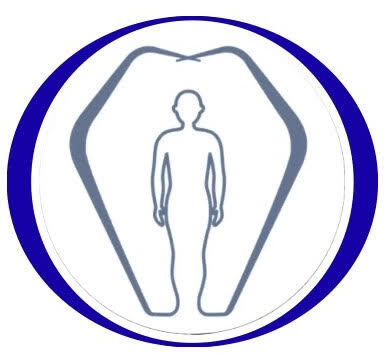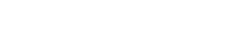インプラントは、どれくらいもつの?
2025年1月16日
裁判の判例と論文をエビデンスとして考察していきます。
インプラントは一生もちますか?
診療室でよく受ける質問のひとつです。結論から言うと、法的にも、永久保証ではありません。
寿命は患者さんの全身状態、清掃、メンテナンスら喫煙ら糖尿病、噛み合わせなどの要因や、埋入する部位や選択する術式によって変わります。
医学的データでは、10年で9割前後の生存が見込めることが多数のシステマティックレビューで示される一方、歯周病、インプラント周囲炎のリスクや、被せ物、スクリュー等の合併症は一定割合で発生します。
このコラムでは、まず、①医学的なインプラントが保存する目安を示す国際エビデンス、さらに、②トラブルがおきた場合に、どこが問題だったのか、日本の裁判の判例もまじえて、③何年もてば法的に責任がないのか? に対する現実的な答えを導くという順番で話していきます。
医学的にはどのくらいもつの?

10年生存はできるのか?
かなり昔のプレートのような板をいれるインプラントではなく、ねじ式のインプラントに限っては、10年時点で概ね94〜96%前後の生存が報告されます。これは複数の様々な独立レビューで反復的に示されていますつまり、適切な診断、手術、補綴、メンテナンス、を行うことを前提とすれのであれば、10年間で約9割台半ばの維持が期待できる、というのが現在の国際的コンセンサスです。
20年生存はできるのか?
最近では、20年のメタ解析も登場し、スクリュー型に限定した再評価で10年を超えると、概ね90%超が持続しうることが示されました。長期間の維持には定期的なフォローが必須です。 10年を超えた後もメンテナンスをかかさないことが推奨されています。
ただ、安心はできません。
実は、生存しているからといって、合併症がゼロではないのです。インプラント周囲炎の有病率は、研究の定義で幅が出るものの“珍しくはないとさせている系統的レビューが増えています。つまり、機能年数が延びるほど生物学的、機械的なトラブルのリスクは蓄積してきますから、長期生存するには、長期管理がどうしても必要になります。
成功基準、つまり、インプラントの成功/生存 を判定する枠組みは時代とともに厳格化してきました。
Albrektsson(1986)基準では、1年目以降の骨吸収0.2mm/年以下で動揺なし、等が採用され、トロント会議(1998)では機能、審美、満足度も追加したより、臨床的な成功指標が示されました。つまり、単に入っているだけではダメで、痛みや感染がないこと、骨吸収が許容範囲であり、患者と術者の満足が得られていることが成功の要件とさせています。
要するに、医学的に保存というのは確率論になります。10年で約95%、20年でも9割前後を目標にすることはできるのですが、合併症は一定割合で起こります。この前提を、術前から丁寧に、患者さんに説明することが重要だといえるのです。
日本の裁判例は何を見ているのか?

何年もったか、より先に問われることはあるのか?
日本で実際に起きた訴訟を考察していきます。
インプラント関連訴訟の系統的解析では、争点として説明義務、手術手技、適応判断、術後管理が多くみられます、そのなかでも説明義務違反、手技が紛争化しやすいと報告されています。特に2015年以降は治療指針等への言及が増え、ガイドライン等から逸脱する場合は、その理由を診療記録に残す姿勢が重要と示されています。
個別事件を見てみます。、たとえば大阪地裁平成15年1月27日判決は、リスクや短所について十分に伝えず、必ず成功するかのような印象を与えた説明が説明義務違反と評価され、損害賠償の一部認容に至りました。
ここで裁判所が重視したのは経過中の痛みの訴えの評価と適応、手技、説明の在り方です。「何年持ったか」を直接の免責要件とはしていないことが注目すべきところになります。
さらに、日本全体の歯科訴訟をみてみると、歯科領域では説明義務が法的責任の判断に強く影響しており、歯科訴訟は医療訴訟全体の約1割を占めると指摘されています。情報提供、同意の質と記録は、法廷でもっとも可視化されやすい論点になります。
まとめると、裁判は保存できた年数の期間で自動に白黒をつける場ではありません。適応判断、説明、手技、術後管理というプロセスがまず問われて、因果関係が審理されるのです。
何年もてば法的に責任を問われないのか?への答え
日本法に、インプラントが何年以上持てば歯科医は免責とする規定は今のところ、ありません。
裁判所は、診療契約上・不法行為上の注意義務、つまり、適応、手技、説明、術後管理を十分に尽くしたか。また、合併症や破損が発生した場合に、そのリスクが予見可能で、適切に説明して対応されていたか、ということを因果関係を総合して判断しているようです。
また、時効も重要です。2020年民法改正後は、被害者が損害と加害者を知った時から原則5年、または医療行為の時から20年で不法行為に基づく損害賠償請求権は時効になります。つまり、20年持てば免責という意味ではなく、請求可能期間には限界がある、ということです。
なお、医院独自の、保証書、5〜10年とかに設定されますが、これは自費診療の商慣行であって法定義務ではありません。保証条件としては、定期メンテ受診、禁煙遵守、過失破損の除外など、補償対象の範囲と、上限額は医院で異なり、保証=法的免責ではないことも知っておいてください。
つまり、何年もったかは、裁判では、それだけの理由では争点にならない。
医学的に、問題ないという目安はあるのか?
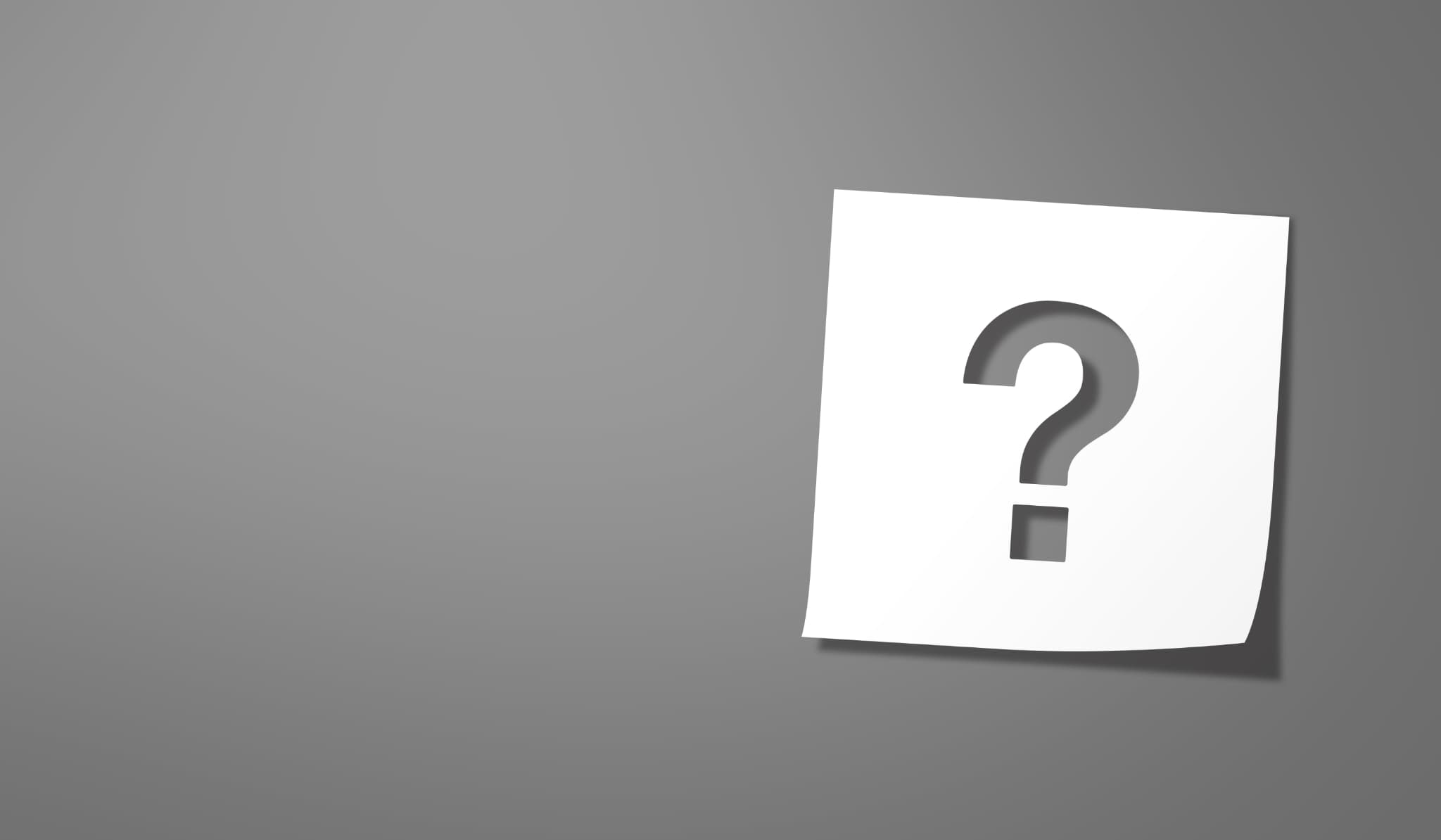
研究的には、10年で約95%の生存は、現在の標準的条件下で、達成可能な期待値です。ただ、20年でも9割超の生存が報告されていますが、長期では周囲炎や補綴合併症が累積するため、定期メンテナンスをしてはじめて問題なしと言えると思います。
したがって医学的説明では、次の3点が重要となります。これがわかれば、患者さんの理解と法的リスクの低減に役立たと思います。
統計値として10年で約95%、20年でも高い維持が期待できると言われているが、合併症ゼロは約束できない。
成功基準として、疼痛、感染なし、動揺なし、骨吸収0.2mm/年以下、機能、審美、満足 を合意済みの評価軸として患者さんと共有する。
また、インプラント周囲炎は珍しくものではなく、喫煙、清掃不良、糖尿病、噛み合わせのストレスなど のインプラント自体ではなく、インプラントにかかわる修飾因子を、患者側と医療側の二人三脚でコントロールしていく必要があります。
説明と記録、メンテナンス契約

説明義務は裁判例上の焦点であり、丁寧に構造化することが最も必要です。具体的には、
- 期待寿命には幅があり、10年生存約95%、20年でも高率だが合併症はあるという基準。
- 主要なリスクとして、術中・術後合併症、周囲炎、被せ物の破損、感覚異常の可能性がある
- 患者側条件としては、禁煙、糖尿病コントロール、プラークコントロールの重要性を知ってもらう
- 定期メンテ受診を前提とした“保証の条件”
想定外事象時の連絡などを書面化・署名化し、カルテに時系列で保管します。裁判例レビューは、ガイドラインに触れた判旨が増えたことを示しており、標準治療からの逸脱した場合は、根拠を記録することが賢明といえるのです。
保証の位置づけも誤解な異様にする必要があります。商慣行としての5〜10年、と説明し、保証条件、たとえば、来院頻度、セルフケア遵守、と除外事由を明示するべきといえます。
最後に、医療行為に関する損害賠償請求は、知った時から原則5年・行為から20年 と、民法改正後の枠組みを把握しておくことで、万一の相談対応が落ち着くと思います。
最後に、
年数ではなく、プロセスと合意

医学的には、10年で約95%の生存、20年でも高率が複数レビューで支持されますが、インプラント周囲炎等の合併症は一定で、長期はメンテ前提の治療。となります。
法的には、何年持てば免責、という固定基準は存在しません。裁判は適応、説明、手技、術後管理の適切さ、因果関係で判断します。 説明義務は特に重視される。
時効は知った時から原則5年/行為から20年。免責年数ではなく、請求期間の限界です。
保証は商慣行として5〜10年が多いが、法定ではない。条件明示と記録が肝心となります。
したがって、統計上の長期維持は十分期待できるが、合併症の可能性とインプラントは管理医療である、と説明して、成功基準とフォロー条件を合意する必要があります。
最後まで、読んでくださってありがとうございました。
今回は、あくまで、インプラントはどのくらい保つ、に焦点をあててお話ししました。誤解がないようにお話ししますが、私は決してインプラントをすすめているわけではありません。
インプラントは、利点もありますが、欠点もいくつかあります。実は、そのことが非常に問題であると考えています。
また、別のお話として、ご紹介しますから、楽しみに待っていてください。
統括院長 Dr.Ryo
このコラムは、ウエスト歯科クリニック、玉川中央歯科クリニックのホームページで、別の内容で掲載されていますので、ぜひ併せてご覧ください。
参考文献・資料(抜粋)
- Long-term (10-year) dental implant survival: Systematic review(10年生存の総説)。10年で概ね94–96%。
- 20-year meta-analysis of dental implant survival(20年メタ解析)。10年超でも高い生存、長期フォロー必須。
- Peri-implantitis prevalence systematic review(周囲炎の有病率;定義により幅)。“珍しくない”合併症。
- Albrektsson基準・トロント会議:成功の判定枠組みの歴史と現行理解。
- 日本のインプラント裁判例の法的解析(J-STAGE)。説明義務・手技・適応・術後管理が中核争点。
- 大阪地判平成15年1月27日(説明義務違反を認定)。「必ず成功」的説明は危険。
- 歯科の法的責任と説明義務に関する日本の実証研究(SciDirect)。歯科訴訟は医療全体の約1割、説明の質が鍵。
- 医療過誤の消滅時効:知った時から5年/行為から20年(2020民法改正・法務省資料、最新の弁護士解説)。
- インプラント保証の実務(5〜10年は商慣行)。